かけだし情報1265
- gabarehiroba2
- 2021年10月21日
- 読了時間: 4分
畑情報
今年は立春が2月3日になり、節分はその前日の2日となります。節分が2月2日になるのは1897年以来、124年ぶりとのことです。立春になってもまだ冷たい北風が吹き、寒さも厳しい日が続いていきますが、天気も徐々に周期的に変わるようになり、春を感じることも増えてくるかもしれません。
少しずつですが、日暮れの時間も伸びてきて昼間の時間が長くなってきます。そうなると畑のアブラナ科野菜は春を感じて花を咲かせる準備を始めます。もう少し収穫できるかな、と思っていると葉っぱの中心に小さな蕾が見えてきます。やがて茎が伸びて蕾がはっきりしてトウがたってきます。このトウの立ったところはかき菜として春の味を楽しむことができます。今年は季節の進み方が早いという天気予報もあり、2月中頃から4月にかけて野菜が少なく心配もでてきました。
そこで、例年よりも少し早めですが、ビニールハウス内に大根、かぶ、小松菜、水菜の種を播きました。
大根は春播き専用の種を使い、ビニールのマルチを張って地温があがるようにしています。土が乾いたら散水していますが、雨が降る予報がでたら天井のビニールを天井中央部分までめくり、しっかりと雨にあてたりと思っています。
ここで少し種の話を。大根や小松菜、ニンジンなど今では一年中スーパーで購入することが可能です。野菜の種まきをするときに、日本列島は北海道から九州、沖縄まで寒い地域から温暖地、暖地と野菜の生育区分をおおよそ3つに分けて考えています。埼玉は温暖地に含まれます。同じ野菜でも埼玉で種を播ける時期と九州などの団地では少し時期がずれてきます。このずれをうまく使うことでスーパーなどでは野菜が切れることがなく店頭に並びます。
ただ、例えば大根でも、品種によって秋播き専用のもの、春に播くものと違います。秋播き専用の品種を春に播くとすぐにトウが立ってしまい、大根とし収穫することができないからです。大根のように明確に春播き、秋播きと分かれていれば良いのですが、野菜によっては温度が上がっただけで花が咲いてしまうこともあります。
何年か前、サニーレタスを育てていた農家が収穫前にトウが立ってしまい、出荷することができなかったという話を聞きました。毎年同じ品種を育てていて初めての事だったそうです。その年は季節の進みが早く、梅雨明けが早くて一気に温度が上昇した年でした。今では気象予報もだいぶ先までわかるようになってきましたが、まだ精度としては完全ではなく、農家にとっては予報と違う、ということになります。ある野菜に特化して大規模に栽培していると、こんな時には大打撃です。そこで、多品目の少量栽培が有機農家では多く用いられている栽培形態となるのです。
立春を迎える時期になったこともあり、園芸マット(電気を使った温床マット)で育てた小松菜と水菜を畑に植え付けました。500ほどの穴が開いたトレイに種を播いたのですが、トレイの穴では土が少ないため育苗を続けると苗が老化してしまいます。とはいえ、まだ外の畑は寒さが厳しいためにトンネルをかけて保温しています。このトンネルはビニールに穴が開いているもので、天気によってビニールの裾を開け閉めしなくてもよいものです。保温自体は穴のないほうが良いのですが労力をかけないためにはこちらのほうが良いのです。
このトンネルは幅が90センチ、長さが20メートル弱です。植え付けをした小松菜、水菜はそれぞれ2列ずつで4列です。列の間隔は20センチ、植え付け間隔は約5センチです。ここで500穴のトレイが2つ半ほど必要でした。寒い中で同じような姿勢を取りながら植え付けを進めていると肩が凝ります。時々立ち上がって腕を回しら作業を進めました。まだ畑に直播しても気温が低いために発芽が揃わないことが多いので、使ったトレイにまた種を播き、畑に植え付けをしていくという作業をもう少し繰り返す予定です。そのうち気温も上がってきて、作業が気持ち良くなる日もそれほど遠くはない気がします。

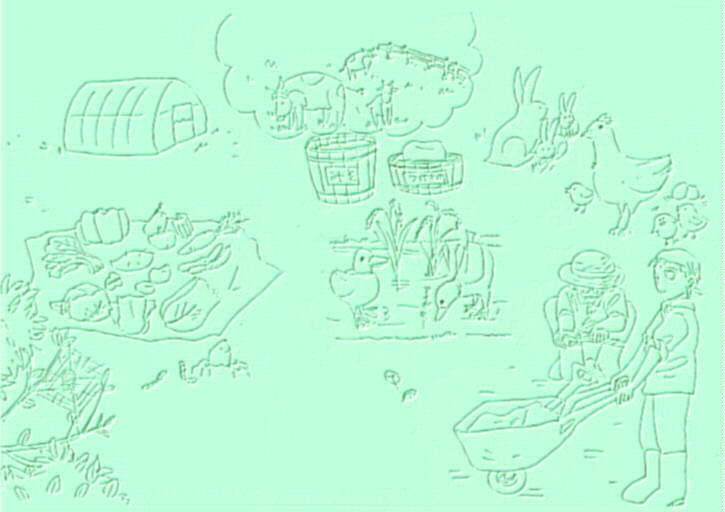


コメント