かけだし情報1247
- Hiroaki Ehara
- 2021年1月20日
- 読了時間: 4分
畑情報
お彼岸を迎え、ようやく厳しい暑さも収まってきました。まだ30度を超える日はありそうですが、朝夕は涼しさが増してくるため、今までの猛暑が懐かしく思われるかもしれません。ただ、すっきりとはしないお天気が続いていて、農作業は天気予報を確認しながら段取りをつけることが多くなっています。
先週の金曜日にはキヌヒカリというお米の稲刈り作業をしました。予報では35度を超える猛暑日だったのですが、太陽は顔を出さず、思ったほど気温は上がりませんでした。曇った分、蒸し暑さが増してしまい、作業をしながらの水分補給が欠かせない1日でした。
このキヌヒカリを育てている田んぼの周辺にはジャンボタニシがうじゃうじゃいます。前にもこの情報で書きましたが、もともと食用として輸入されたジャンボタニシが野生化し、今では田植え後のイネを食害する困った生物となっているのです。1匹のジャンボタニシが産卵する数は2000個以上、冬も越冬するため根絶するのが難しいと言われています。ジャンボタニシが生息する地域の農家などは、産み付けられたピンク色の卵を水路に掻き落とす作業を繰り返していますが、すぐに別の卵が産みつけられてしまい、これは、という解決策が見つかりません。
食害されるのは稚苗と呼ばれる種まきからあまり日数の経っていない小さな苗が多く、20センチほどになった成苗を植えれば被害は少ないと言われます。ただ、ほとんど農家の栽培体系は成苗を植えるようにはなっていないので、すぐに成苗に切り替えるのも難しいのです。稲刈りをしていても、刈り取る稲株の下の方にピンク色の卵がついているものもありました。
このジャンボタニシは年々被害地域を広げているので、どうにかしないといけません。
このジャンボタニシは稲にとっては害虫ですが、実は田んぼには本当に多くの生き物が生きています。加須の有機稲作農家が書いたコラムですが、彼の田んぼは水路から生き物が昇ってこられるように魚道をつけたそうです。この魚道を登ってくるのはドジョウ、メダカ、フナ、鯉、アメリカザリガニ、ウシガエル、ギンヤンマのヤゴなどなど、その種類の多さにびっくりしたとか。
田んぼはこのような生き物の餌となるユスリカの幼虫やミジンコなどがたくさんいます。ただ、その生息数は慣行栽培の田んぼと有機の田んぼでは大きな違いがでることも報告されています。もちろん、有機の田んぼのほうが生き物の種類、数とも多いという結果となります。
彼は、田んぼはただ単にお米を獲るだけの場所になってしまったのはいつからだろうと言います。多様性が必要だと言われますが、田んぼは多様性に満ちた場所でした。米を育てるのはもちろんのこと、条件の良い田んぼであればドジョウやカエルなど、昔であれば貴重なたんぱく源となった生き物も育っていたことになります。また、夏の暑い日、田んぼに井戸水が入ると冷たい風が吹き抜け、暑さを少しだけ和らげてくれます。うちの前の田んぼの合鴨に至っては、田んぼにいるだけで癒しの対象となり、それまで田んぼを見ることをしなかった人たちを引き付ける場所ともなります。田んぼはとても魅力的な場所だったのです。
稲刈りをしたキヌヒカリですが、今年から栽培方法は、埼玉県の特別栽培米の基準に準じたものにしています。昨年までは化学肥料を田植えと同時に施肥し、それで終わりでした。今では主流となっている一発肥料というもので、コーティングされた肥料が時間によって溶け出してくるため、穂肥などの追肥をする必要のないものです。ただ、このコーティングには特殊なプラスチックが使われているようで、マイクロプラスチックの問題が出ている中で、使うのを避けようと考えました。
今年は、代掻きの前に発酵鶏糞と有機100%の肥料を散布し、穂の出る前には有機100%の肥料を穂肥として散布しました。田植えの時に2成分の入っている除草剤は使っています。肥料の成分は100%有機のものだけで育てたキヌヒカリですが、収量は昨年のそれほど変わりませんでした。
来年は田んぼにレンゲの種を播き、それを緑肥として米つくりをしようと考えています。近所の養蜂をしている方も、レンゲを栽培してくれる農家を探しているとのことで、養蜂とのコラボ米ができるかも?
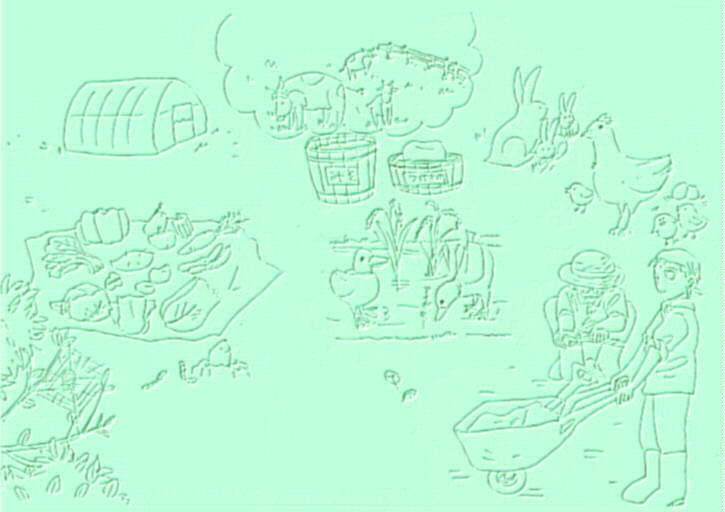


コメント