かけだし情報1239
- Hiroaki Ehara
- 2021年1月20日
- 読了時間: 4分
畑情報
梅雨明けは8月にずれ込む可能性もでてきました。
いつもの年であれば7月の20日頃は梅雨が明け、猛烈な暑さが10日ほど続く猛暑のスタート時点です。
ところが、今年はなかなか太陽が顔を出しません。日曜日から月曜日にかけてはようやく晴れ間が見えましたが、また梅雨空にもどってしまうような曇りマークが並んでいます。
21日は土用、ウナギを食べ夏を乗り切る体力をつける日です。6月につけていた梅も子のころには天日に干して梅干しとなります。稲も土用干しといい、田んぼから水を抜いて乾かす時期です。このタイミングで梅雨から一気に夏に代わる節目の日なのでしょうが、今年はどうにも感じが違います。
稲は太陽がでないために例年よりも1週間ほど生育が遅いという話を聞きました。この時期は田んぼの水をいったん抜いて乾かし、土の表面に軽い日々が入るくらいまで干したら、再び水を入れる中干しと呼ばれる作業があります。ちょうど土用の頃に行われるのが一般的だったことから土用干しとも呼ばれます。ただし、今は田植えの時期も早くなり、土用の頃には早い地域では穂が出始める所もありますから、中干しイコール土用とはならないようです。
中干しをする理由はいくつかあります。それまで水を張った中で育っていた稲は分けつと言って茎を増やしていきます。ただあまり茎の数が増えてしまうと
ひとつの株が多くなりすぎて、その後の生育が弱くなったりします。そこで水を切ることで分けつを止めて、その後の生育がしっかりしたものになるようにするのです。また、土の中にあるガスを抜き、根が健全に育つようになることや、いったん土が固くなるので、その後水を入れても稲刈りの時に機械作業がしやすくなることも中干しをする理由のひとつです。
ただ、今年は中干しをしたくても毎日のように雨が降っていたために、なかなか田んぼが乾きません。溝を切って水が流れ出やすくする作業も奨励されていますが、機械がないと手作業では無理な広さです。ある程度乾くまで水を入れないでおければよいのですが、稲が穂を出すときには十分な水が必要となるため、穂の出る2週間前には水を入れる必要が出てきます。
梅雨明けが遅れることで作業の段取りも遅れてしまうと、穂肥をやるタイミングなども難しくなってい
きます。
イネは穂を出す3週間ほど前になると穂の赤ちゃんである幼穂を確認することができるようになります。もちろん外から見ただけではわからないので、田んぼから成長が良いものを取ってきて茎の下部をナイフで半分に切ります。そうするととても小さな穂の赤ちゃんをみることができます。この幼穂の長さによって、あと何日で穂を出すかを推測します。
また、葉っぱの色が7段階に分かれている葉色判断用のものを使って、肥料が効いているか、あるいは足りないかを判断します。葉っぱの色が7段階のうち4~5であれば穂肥という追肥をしても大丈夫ですが、それよりも濃い色だと肥料が効きすぎて倒伏する恐れがあるので、穂肥は少し遅らせるか、やらないという判断をする基準となります。
昨年までは有機以外の田んぼは化学肥料を施肥し、それも段階的に効果が出てくるものだったため、穂肥をする必要がありませんでした。今年から有機以外の田んぼは特別栽培米の基準にしています。そのため、最初に入れた肥料は発酵鶏糞と有機100%の肥料です。穂肥には品種によって有機100%のものと、化学肥料とに分けていますが、いずれもそろそろ追肥の時期に来ているので、いつ頃に肥料を入れるかの判断をするために幼穂の状況と、葉っぱの色の判定をしたのです。
地域の田んぼを見渡しても、植えた時期や品種によって稲の生育も違います。太陽が出ていないため、全体的に伸びすぎているような田んぼもありますが、家の前の合鴨の田んぼのように、やっと稲の葉っぱが濃い色になり始めてところもあり、稲を育てることの奥深さを改めて感じている今年のイネ作りです。
雨の影響は畑にも出ています。特に雑草の伸び方は半端なく、刈りたくても器械が入れないほどぐちゃぐちゃな状態でした。ここ数日、雨はそれほどでもなく、太陽も出たので、すぐにでも耕しておく必要のある畑から草刈りをしています。トレイに播いた大豆は芽を出し、今週末くらいには畑に植え付けないといけません。また、人参も種まき時期になっているため、こちらも早く耕して種まきの準備を進めたいところです。
雨の嫌いなトマトは収穫前に皮が破れたり、傷んだりしたものが多く出てしまいましたが、これから太陽がでると一気に色づいてきます。多めにトマトが欲しい方はお声がけください。
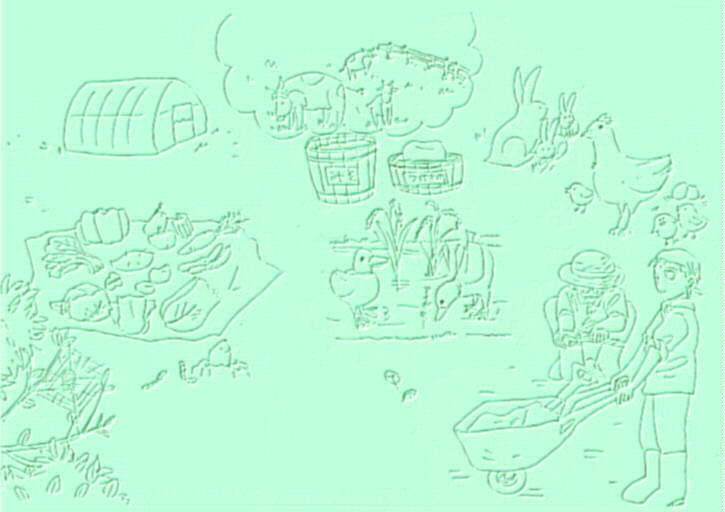


コメント