かけだし情報1236
- Hiroaki Ehara
- 2021年1月20日
- 読了時間: 3分
畑情報
日曜日の雨は思いのほか大雨となりました。今年の梅雨は雨が多く、田んぼの水管理は楽ですが、畑に入ろうと思っても、雨が降ってしまい作業ができない状態が続いています。それでも後2週間もすれば暑い、暑い夏がやってきます。今年もしばらく37度を超えるような猛暑が続くのでしょうか?
さて、先週のかけだし情報で書いたジャンボタニシについてです。画像はネットからとったものですが、普通のタニシに比べると数倍の大きさになるタニシです。ジャンボタニシは通称で、本当の名前はスクミリンゴガイと言います。自然の中では南アメリカのラプラタ川に生息しているそうで、日本へは1981年に台湾から食用として長崎と和歌山に持ち込まれました。その後、全国に500か所近い養殖所ができたのですが、採算が取れないことなどから閉所となるところが多く、そのまま野生化していったのが、全国に広がった要因です。
このジャンボタニシは体内に寄生虫を宿していることがあるため、生食は危険です。また卵にも毒があり、素手で触ることも危険と言われています。
ところで、食用として持ち込まれたこのジャンボタニシ、味はどうなんでしょうか?テレビの番組でトキオのメンバーがジャンボタニシを調理して食べるというコーナーがありました。また、ネットでもジャンボタニシを食べた、という記事がアップされていたりします。寄生虫のことも考えてしっかりとした処理し、味付けをすれば美味しく食べることができるということです。
このジャンボタニシ、田んぼに植えたばかりのイネの苗を食べてしまう厄介者です。ただ、水管理をすることで雑草を食べてくれる農薬いらずの米つくりの救世主となっているところもあるのです。その水管理ですが、田植え後はほぼ水がない状態にしておき、その後1ミリ単位で水位を上げていくのだとか。田んぼが均一に平らになっていることが絶対条件でもあり、農家にとってはかなり高度な技を必要としています。
田んぼに植えた稲よりも、生えてくる雑草のほうが柔らかいため、ジャンボタニシは雑草を食べてくれ、その間に稲は成長してジャンボタニシの食害から逃れることができるということです。
うちの田んぼのある周辺でも、水路の壁や稲の茎のところなどにピンク色の卵が産みつけられています。
一匹のジャンボタニシが産卵する数は2000から8000個、急速に個体数を拡大させている理由の一つは天敵がいないことです。ジャンボタニシの天敵はスッポンやカルガモ、アヒルなどです。被害の多い地域では水路にアヒルを放してみたり、スッポンを放しているところもあるようですが、スッポンなどはいつの間にか誰かに盗まれたりする被害もあるとか。なかなか思い通りには行きません。田んぼの一部が食害の被害を受けたところも何か所か出ているため、対策が急務となっています。鴻巣市では、この被害の多い地域にコウノトリの飼育施設を建設する計画があります。もしかするとコウノトリの餌としてジャンボタニシが使えるかもしれません。
一方、畑の方はというと、ナスやピーマンの週っ格が始まり、キュウリもとれるようになってきました。トマトはこれから熟していく段階になっていますので、7月に入り、太陽が顔を出してくれるようになると色づきがすすむと思います。
今年の冬には味噌を仕込む予定になっているので、大豆も育てることにしています。畑に直播をすることもありますが、雨で耕すことができないので、トレイに種を播き、その後畑に植えかえることになりそうです。そして7月も中旬になると秋冬用の人参の種まきも始まります。少しずつ時期をずらして何度かに分けて種を播きますが、梅雨の残っている時期に播くことができると発芽に必要な水分を確保できます。この後のお天気がどうなるかはわかりませんが、お天気と相談しながらの作業になっていきます。

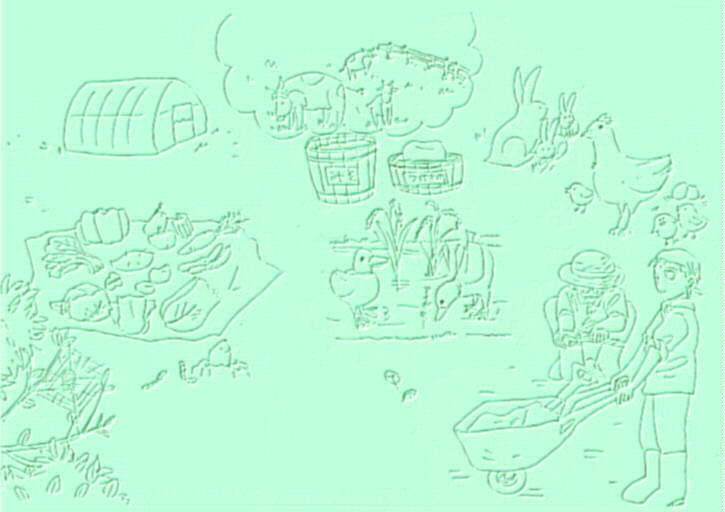


コメント