かけだし情報1232
- Hiroaki Ehara
- 2021年1月20日
- 読了時間: 4分
畑情報
梅雨の季節がやってきました。これからは雨と蒸し暑さの日が多くなってきます。新型コロナウイルスの緊急事態宣言は解除されましたが、第2波を思わせる感染も出てきていますから、まだまだ安心して日常を取り戻すことはできない感じです。ウイルスは高温多湿には弱いと言われますが、熱帯地域でも発生が確認されていますから、密な状態を避けることが必要です。
毎年、多くの家族連れの方に参加して頂く、田植えのイベントも今年は中止です。合鴨が田んぼを泳ぐころには落ち着いていれば良いのですが。
今年も合鴨がやってきました。先週の水曜日に大阪から宅急便に運ばれてきました。着いてしばらく落ち着かせたら、砂糖水を口に含ませて育雛小屋に入れました。水鳥である合鴨はおしりのところに油の出る腺があり、その油を羽に塗ることで水を弾き体が濡れることを防ぎます。ただ、赤ちゃんの合鴨たちはまだ十分にその機能を使うことができないため、しばらくは水慣らしの訓練が必要です。
収穫用のコンテナに合鴨たちを入れ、田んぼの水についてあげます。着いた初日は5分ほどで引き揚げますが、だんだんと時間を長くしていきます。最初のうちは羽全体を濡らしていた合鴨もいましたが、だんだんと水に慣れ、田んぼから小屋に戻ると小さなくちばしで油を塗るしぐさを見せるようになってきます。
田植えをしてから1週間ほどで田んぼに放すので、それまで段階を追って水慣らしをしていきます。最初の1週間はコンテナの中での水慣らしをし、その後は田んぼにある合鴨の小屋に日中は入れるようにします。ここは休憩場所と田んぼの水がすぐそこにあるので、合鴨たちは自由に水場と休憩場所を往復できます。
小屋の周囲はネットで囲っているので、田んぼに出ていくことはないのですが、時々ネットの隙間から田んぼへと出てしまうやんちゃな鴨もいて、捕まえるのが大変な時もあります。今月の第2週目が田植えなので、合鴨たちが田んぼデビューするのは14日頃からです。
その田んぼでは、今田植えの前の作業である代掻きを進めています。それまで水のなかった田んぼに井戸水などの水を入れ、全体に水が行きわたったらトラクターにハローという代掻き用のロータリーをつけて田んぼを耕します。水を含んだ土を細かくし、田植えがしやすいように田面を平らにするのが代掻きです。
農家によっても異なりますが、一般的に代掻きは2回行います。まず、荒代といい、土と水をしっかりと混ぜることを目的とします。耕された部分と、その下のところで層が作られ、水が抜けにくくなるのです。
そしてその後に植え代という総仕上げ的な代掻きをして、2~3日後に田植えをするというのがパターンです。荒代から植え代までの期間は数日の農家もいますが、うちでは1週間~2週間の間を取っています。それは、水が入ったことで雑草が眠りから覚めてくるからです。田植えの前に、芽の出た雑草を埋め込むことも植え代の目的です。
代掻き作業は時速1.5キロほどのゆっくりした速度で作業をします。大きな田んぼではトラクターのエンジン音と振動が心地よくなり、つい眠気に誘われることもありますが、そんな時は田んぼの様子を観察することにしています。土の中にいたカエルたちが慌てて逃げだし、それを目当てに集まってきたカラスやサギなどの鳥たちの動きを観察するのも楽しい時間です。
田んぼの中にはすでにカブトエビやオタマジャクシ、ミズスマシやアメンボなどの水生の生き物が動き回っています。小川とつながっているような田んぼでは、生き物の数や種類はもって多いようですが、ミジンコなどの微生物も含めると、田んぼの中には無数の小さな命が存在します。お米が育つのも、このような多くの生き物が田んぼにいることが必要になります。
今、田んぼは麦が色づいているところ、田植えが終わって苗の緑が目立つところ、水の入っていない茶色の土のところ、水が入っているところなど様々な彩りを見ることができます。

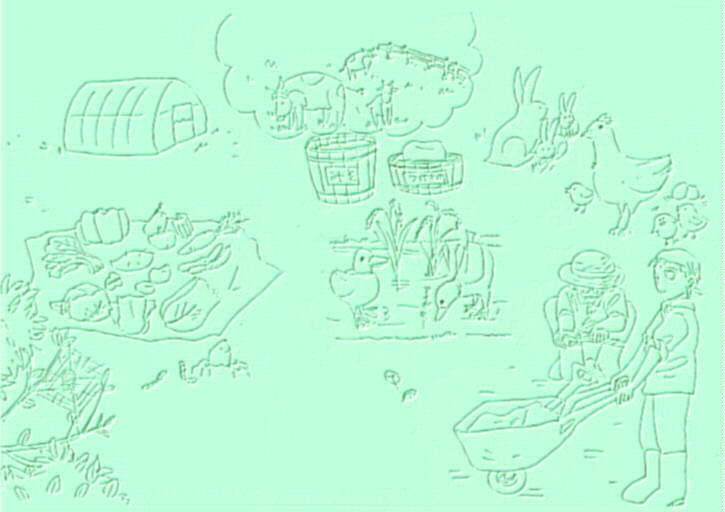


コメント