かけだし情報1221
- Hiroaki Ehara
- 2020年4月11日
- 読了時間: 4分
畑情報
新型コロナウイルスが社会に大きな不安をもたらしています。学校が突然休校となり、子どもたちの居場所や親の働き方など混乱も大きくなり、経済や物の移動にも影響がでています。早く収束することを願うばかりです。
暦は3月となり、農作業も忙しい季節が始まります。
モスクワではこれまでにない暖冬で、降雪もほとんどなく、観測史上最も暖かい冬となった、との記事がでていました。ここ数日は寒気の影響などで強い季節風が吹いたりしましたが、太陽の光は冬のそれとは違い、春を思わせるようなものになっています。暖かい冬は、雪解け水を田んぼに利用している地域では、これから始まる米つくりに水の心配をすることになるかもしれません。また、もう少し畑で育ってほしかったアブラナ科の野菜は早めにトウが立ち始め、つぼみから花へと次世代の種を残すための動きも早くなっています。3月の半ばごろまで収穫を見込んでいた葉物野菜も早めに終わってしまいそうです。
一方で、例年よりも生育が早くなりそうな野菜の管理も前倒しで進めることになりそうです。エンドウなども寒い冬では枯死するものがありますが、今年は元気に育っています。早めに支柱を準備するようです。
冬に植え付けたキャベツには防虫ネットをかけました。そろそろ飛び始めるモンシロチョウが卵を産み付けるのを防ぐ目的もありますが、畑の周りをウロウロしている鳥たち、とくにムクドリなどに見つかると、あっという間に葉っぱをたべられてしまいます。鳥の食害を防ぐのも防虫ネットをかける目的のひとつとなります。
育苗ハウスのなかでは、踏み込み温床を作り、先週にはナスとピーマンの種を播きました。朝方はハウスの中も外気とそれほど温度は変わりませんが、日中になると、ハウス内は35度を超える日も出てきます。
踏み込み温床は、落ち葉に米ぬかや鶏糞堆肥を混ぜて、水をかけながら踏み込むという作業を何回も繰り返し、落ち葉堆肥を枠の中で作るものです。落ち葉が米ぬかなどの力を利用して発酵し、その発酵熱を利用することで、高い温度が発芽に必要な夏野菜、ナスやピーマン、トマトなどを育てるためのものです。
踏み込み温床は、表面から10センチほど下の部分で温度が30~40度になっています。踏み込んで2日後くらいから熱が出始め、やがて50度を超えるくらいまで上昇します。微生物が一生懸命に働いている証拠です。やがて上昇した温度が下がり始め、30~40度ほどになったことを確認してから、種を播いたトレイを温床の上に置いておきます。ナスやピーマンは発芽までに時間がかかりますから、まだ今の時点で発芽はしていません。今週の半ばくらいから少しずつ発芽が始まればと考えています。

上の写真は温床、ナス、ピーマンの種を播いたトレイを置いているものです。夜にはビニールをかけて保温し、日中は曇りや雨の日はビニールはそのままかけていますが、晴天時には外して温度の調整をしています。この温床の隣も落ち葉を踏み込んでいるので、来週になるとトマトの種をまくことができそうです。そのあとは、次の温床を準備し、キュウリやカボチャなどの瓜類を播いていきます。
育苗ハウスの中では、他にも葉物野菜の種を播いたトレイを棚の上に置いています。小松菜や水菜など、そろそろ露地に直接播けるものもありますが、ちょうど雑草も発芽を始めるタイミングにもなるため、最近では育苗ハウスで苗を育て、ある程度の大きさになったものを畑に植え付けるという方法をとっています。
育苗ハウスの中で種まきなどの作業をする場合は、半袖のTシャツがちょうど良い感じです。気温が30度を超えているので、真夏のようなものです。ただし、何かの用事でハウスから出ると冷たい北風が吹いている時などは一気に汗が冷えてしまいます。この時期は、少し動くと汗ばむこともあるので、体調を管理するのも大変です。
今週はお天気にもよりますが、ジャガイモの植え付け、田んぼの荒起こしなど忙しくなりそうです。外の作業が気持ち良い季節になってきます。
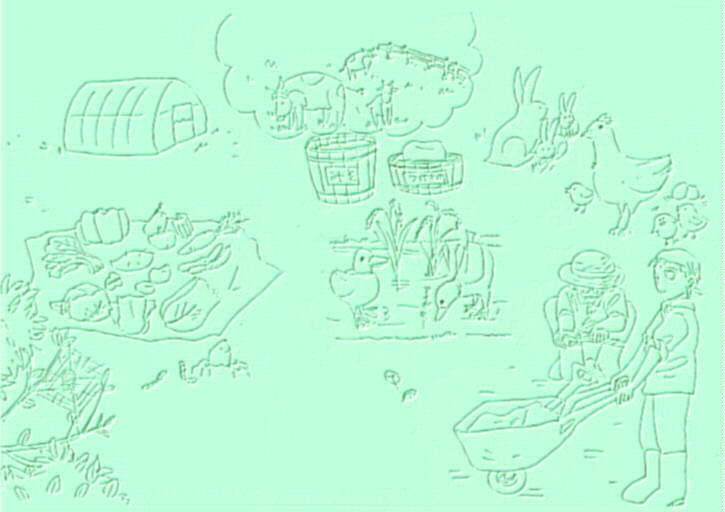


コメント