かけだし情報1212
- Hiroaki Ehara
- 2019年12月17日
- 読了時間: 4分
畑情報
年号が新しくなった年も残すところ2週間です。12月に入っても全般的に気温が高めな日が多く、師走特有の慌ただしさを感じる気持ちと気温のギャップが大きい気がします。汗ばむようなお天気の翌日は冷たい北風が吹くこともあり、体調の管理も大変です。
ここ2週間ほど、鶏がぱったりと卵を産まなくなっています。冬至までは日が短くなる一方なので、鶏たちも冬を感じて産卵をやめてしまいます。それが過ぎればまた産み出すと思いますので、もうしばらくお待ちください。
11月に届いたヒヨコたちも小屋の中に設置した育雛箱が狭くなってきました。約30センチほどのある板も軽くジャンプして飛び越えてしまうので、ヒヨコが飛び出ないように金網を付けた天井板を載せています。それでも、天井板と周囲をかこっている板の間のわずかな隙間から飛び出すヒヨコが毎日数羽います。捕まえては箱の中に戻していましたが、結局、周囲の板も天井板も取り除くことにしました。
箱の中がだんだんと狭くなってきたことと、数羽のヒヨコが調子が悪くなっていたからです。寒さを防ぐために入れていたこたつの暖房はスイッチを切っていましたが、狭い空間に100羽のヒヨコがいるだけでも箱の中は新鮮な空気の流れが阻害されてしまいます。冬の気候にも慣れてきたので、育雛小屋のなかに開放することにしたのです。
それでも体が少しずつ成長しているヒヨコにはもう2週間ほどで、育雛小屋も狭いものになってしまいます。ひよこが入る予定の鶏小屋はまだ鶏糞が3分の1ほど取り出せていないので、早急に鶏糞をだし、新しくもみ殻と藁を敷き詰めてヒヨコを移動させたいと思います。
畑の作業もまだ残っています。育苗ハウスで苗を育てている小松菜や水菜は半分ほどは畑に植えました。まだ本葉が2枚程度出たばかりの小さな苗ですが、畑に植えて、植え終わったら穴のあいたビニールトンネルを掛けることにしています。
また、ちょっと種まきが遅れた絹さやも畑に植え付けました。絹さやは冬の寒さにあたるほうが春先に生育が良くなります。とはいえ、強い北風によって茎が折れたりすることもあるので、暴風をかねて防虫ネットのトンネル掛けをしました。
また、苗を育てていたキャベツも植え付けをしました。まだ本葉が4枚ほどの小さな苗です。収穫できるのは来年の5月頃ですから、まだまだ先の長い話です。
先週は、やっと大豆とサツマイモの収穫がおわりました。大豆は台風で水に浸かった時間が長かったので厳しいと思ったのですが、味噌を仕込むだけの量は難しいものの、来年の種くらいは確保できそうです。ただ、小粒の黒豆は背丈も低いこともあり、莢ばかりで実がほとんど入っていませんでした。サツマイモも例年よりも出来は良くないものの、ある程度の収穫はありました。春先にむけて貯蔵をするのですが、腐ってしまうものもあり、今のうちに食べて頂くほうが良いようです。そのままでもスィーツにしても良いので、サツマイモを料理に使ってみてください。
さて、今日は社会福祉協議会の地区支部の集まりがありました。地域の福祉関連の委員をしている人たちが集まり、地域の問題等についての研修をうけました。
2025年は団塊の世代が75歳を迎える年で、その時に起こる問題を2025年問題と言います。日本国民の3人にひとりが65歳以上、5人に1人が75歳以上になります。同時に15歳から64歳の現役人口も減少し、介護人材の不足、医療・介護施設の不足、医療費や介護保険料の問題などが指摘されています。
昨年より地域の農地保全の組織ができ、農家と農家以外の約40名がメンバーとなって農地の草刈りや農道、水路の整備などをしています。国からの補助金を使っていて、作業に参加すると若干の日当も支払うことができる制度です。この団体と地区の田んぼを一手に引き受けている担い手農家との話し合いもありました。2025年問題と同様、農家も高齢化が進み、田んぼを大規模に整備できるところは担い手によって農業が続けることができますが、宅地周りの小さな面積の田んぼや畑は大規模化することができません。
現在主力の70代が6年後には後期高齢者となります。やがて虫食いのように遊休地、空き家がでてくることは確実で、今から何らかの手を打たないといけないという議論になりました。有機農業がその問題を解決する糸口になる気がしています。
12月28日(土)餅つきをします。
合鴨農法で育てたもち米を使って、伸し餅を作ります。ご希望の方には、お分けできますのでご連絡ください。餅は、約1升ぶんで2000円となります。
ご連絡お待ちしています。
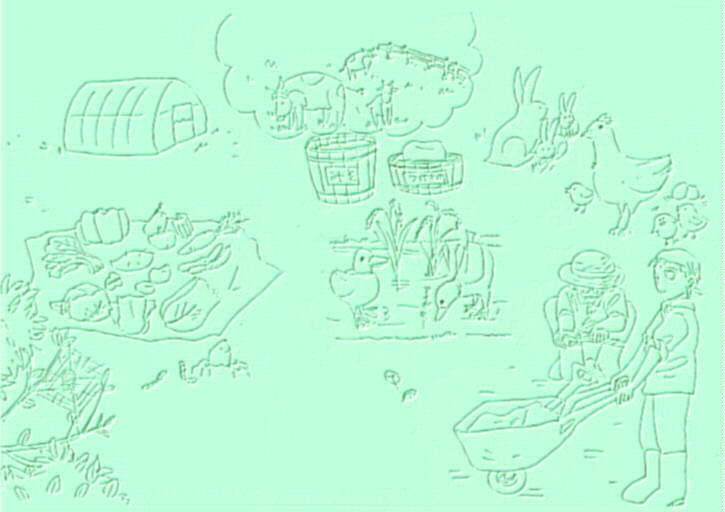


コメント