かけだし情報1203
- Hiroaki Ehara
- 2019年10月24日
- 読了時間: 4分
畑情報
台風19号は静岡、関東、東北に甚大な被害をもたらしました。台風が最接近した時の猛烈な暴風、そして長く降り続いた大雨は、命の危険を本当に感じるものでした。埼玉でも近隣の市町村で河川が氾濫し、多くの人が避難、救助されています。千葉県の台風15号の被害もつい最近の出来事ですが、それ以上の広範囲のでの影響をもたらした19号でした。
ガバレの家前にある田んぼで予定していた稲刈りイベントは台風と重なったために中止となりました。台風が来る前から一部で稲が倒れかけていたのですが、19号の暴風で4分の1ほどがべったりと倒れてしまいました。大雨で冠水していた田んぼのうち1枚は2日後になると水が引きましたが、もう1枚はまだ
水が溜まっている状態です。この水のあるところは稲が倒れているところで、早く稲刈りをしたいのですが、水が引くまで待つことになりそうです。
畑も大雨で冠水し、水が引かないところもでています。降った量も多く、表面の水はなくなっても地中には水分が溜まっています。大根など土の中に深く伸びるものは場合に影響がでてきます。葉物野菜も収穫が始まりましたが、雨と暴風で痛めつけられたものは回復できるかどうか微妙なところです。稲刈りももう少しで終わるところで、野菜も収穫が始まったタイミングでの台風の襲来は、ダメージが大きいものとなりそうです。
台風の暴風は、稲や野菜への影響を与えるほか、農家の施設も心配の対象となります。千葉県の状況を見ると、ビニールハウスがぐちゃぐちゃになる被害が出ていました。ガバレにも育苗用のハウス、トラクターなどの農機具を入れている納屋もシートを張ったハウス状のものを使っています。また、鶏小屋も二つはビニールハウスを利用し、もう一つも屋根に透明のトタンを張った簡単な作りの小屋です。昨年の台風では大きな木が根元から倒れ、鶏小屋のハウスを直撃し、ハウスの後方が大木でつぶされたままとなっています。育苗用のハウスはあらかじめ天井のビニールをはがしておき、暴風による倒壊が内容にしていましたが、心配は鶏小屋や農機具用の納屋でした。幸いなことに心配していたような被害はありませんでしたが、鶏小屋のドアが壊れ、鶏が外に出てしまいましたが、ドアも作り直し、鶏も中に入れることができました。
台風の接近に備え、消防団も消防小屋で待機となりました。所属している分団は荒川に隣接した地域を受け持っており、水防団も兼ねています。定期的に荒川の堤防に出向き、荒川の水位を確認し、それを本部に伝えることが役割のひとつです。
荒川の水位の状況は、荒川上流河川事務所がのウエブサイトで水位の変化と、ライブカメラで現状を確認することができます。ですが、現場で川の流れの速さ、堤防の状態を見ることは必要となります。秩父にあるダムの緊急放流によっても流量は増え、雨が止んだ後も水位が上昇するため油断はできない状況でした。実際に担当している地域の荒川は、堤防の上まで2メートルを切るくらいまで水位は上がっていました。秩父のダムで新たな緊急放流が実施されていたら、堤防を超える危険もあったと思います。
夜の10時を過ぎ、徐々に暴風が強くなってきました。消防小屋の2階で待機していると、吹き付ける暴風によって小屋の窓や入り口の扉が歪んでしまうことがありました。このままでは窓の破損なども考えられたので、いつもは消防車を格納している一階に避難しました。外に停めている消防車も風にあおられて揺れ、すぐ目の前にある小学校の木々は折れそうな勢いで風に揺れていました。台風の暴風時に外にいることはほとんどありませんから、今回の暴風雨は本当に身の危険を感じるものでした。
消防小屋前にある小学校は夕方6時過ぎくらいから避難所の開設が始まりました。防災無線で緊急避難の呼びかけもあり、消防団も地域に避難の呼びかけに回りました。ただ、避難所開設がとても遅く、周りが暗くなってからだったので、歩いての避難は危険な状況でもありました。農業用の排水路もほぼ道と同じ高さまで水かさが増していましたから、道路が冠水した場合は、道と排水路の区別もわからない状況でした。
停電は発生しなかったものの、雨と風で防災無線の音も聞き取りずらく、夜になって暗くなると不安が一層強くなります。そんな中で、一時的な避難所となった小学校の体育館、そして水害に備えて後者の3階、4階が最終的な避難所となり電気がともると、それまでの不安な気持ちが少し和らぐのを感じました。暗いなかで明かりがつくことがどれだけ人間にとって安心するものであるかを実感しました。温暖化による台風の大型化、強力化はこれからも進むでしょう。
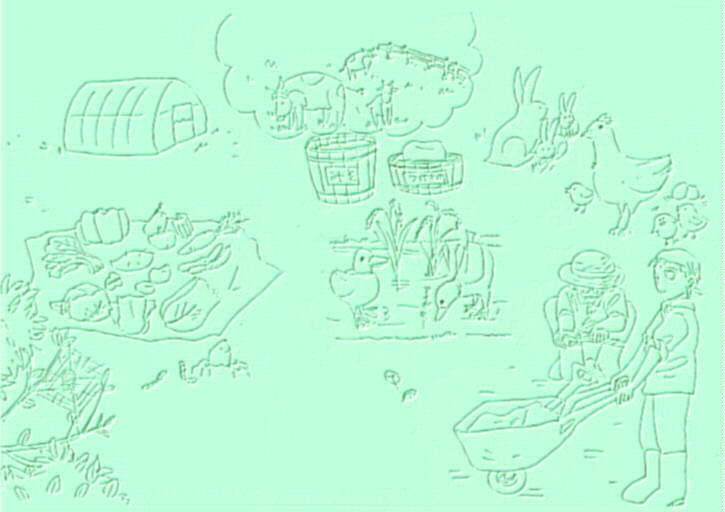


コメント