かけだし情報1202
- Hiroaki Ehara
- 2019年10月24日
- 読了時間: 4分
畑情報
季節外れの暑い日が続きましたが、やっと秋らしい涼しさが戻ってきました。しかし、大型の台風が今週末に日本に近づいてくる予報が出ており、稲刈りのイベントがどうなるか心配です。もし、台風がこちらにも来て、大雨が降った場合は、稲刈りは延期になります。翌週の日曜日にするか、それとも中止にするかはその時の状況次第となりそうです。
ガバレの田んぼは半分は有機、半分はまだ慣行です。稲刈りは早生の品種から始まり、もち米、有機のお米、慣行のお米と進んできています。面積的には3分の2が終わり、残りの3分の1をこれから刈っていきます。
お米を作る農家には当たり前の作業工程も、農家以外の人にとってはなじみのないものだと思いますので、すこし稲刈りについて書いてみたいと思います。
稲を刈るのはコンバインという機械を使うのが一般的です。この機械は刈り取りから脱穀までを行うもので、ほとんどの農家が使っています。もちろん、機械の大きさや性能には違いがあり、作業時間も異なります。先日、長野に行った時には刈り取って稲を天日干ししている地域がありました。比較的広い田んぼでも天日に干している光景が広がっていました。天日干けいりょう機械を使います。天日干しが終わると脱穀作業を行うので、手間が多くかかっています。
コンバインで刈り取り、脱穀した籾は軽トラックなどの荷台に取り付けた運搬用のコンテナに入れて家まで運びます。この時、コンバインを使って稲刈りをする人と、軽トラで運搬する人が別にいれば効率が良くなりますが、一人で刈り取りも運搬もすると時間がかかってしまいます。
軽トラックで家まで運んだ籾は、運搬用のコンテナから乾燥機に移されます。乾燥機は一般的に灯油を使ってバーバーを燃焼させ熱風を発生させます。この熱風で籾を乾燥させていきます。ただ、熱風を使うと急激な乾燥による同割れなどが起こる場合があり、お米の品質を低下させることもあると言われます。
今、うちで使っている乾燥機は、遠赤外線を利用したもので、熱風と組み合わせることで効率よく籾の中の水分を乾燥させてくれるものです。もちろん、天日干しの乾燥のようにじっくりと水分を飛ばすというわけにはいきませんが、お米の品質を少しでも天日干しに近づけることをうたい文句にした乾燥機です。
稲刈りをするときの籾の水分量は25%以下が刈り取りの適期と言われます。乾燥機を使うと、1時間に0.6%ほど水分が下がるように設定されているので、稲刈りをしたときの水分が25%とすると、適度な水分量である14.5%に下げるまでは18時間ほどかかります。できるだけ低温で乾燥させるほうがお米の品質を保つには良いと言われます。
水分量が14.5%になると次は籾摺り作業です。籾摺り機という機械を使って、籾殻を取り除き、お米を玄米状態にする作業です。この籾摺り作業と同時にお米の袋詰め作業も行います。籾摺り機で玄米になったものが計量機という機械に送られ、この機械で良い玄米と未熟な玄米を選別し、良い玄米をお米の袋に詰めていく作業です。出荷は30キロのお米の袋に入れて行います。30キロになると自動的に玄米の排出が止まるので、次の空き袋を準備し、お米を入れるという作業を続けます。
この計量器を使っても、すべての未熟米やもみ殻のついた玄米を取り除くことができません。性能の良いものを使えば可能かもしれませんが、小さな農家では機械にお金を使うことにも限界があります。お米をたくさん作っている大規模な農家は高価な色彩選別機という機械を使い、混じったくず米などを取り除いています。この機械は、きれいな玄米以外で、もみ殻のついているお米や青い未熟米、草のたねなどを一瞬のうちに判断して弾くものです。
お米は1等から2等、等外というランク付けがされていきます。これは味や品質によるランクではなく、見た目によるものです。たとえばカメムシによる食害はお米に黒い斑点ができてしまいます。この黒い斑点があるお米が1000粒のうちに何粒かあると1等ではなく2等となり、買取金額も少なくなります。この等級付けが農薬散布を増長する原因ともいわれ、等級検査の見直しをするべきという議論もありますが、まだ見直しの気配はありません。
今は、農家が直接お米を販売することができますが、まだほとんどの農家がJAやお米屋さんに出荷し、そこからお米の問屋などへと流通していきます。農家が直接売るのではない場合、多くの収量があるほうが農家の収入も増えるので、品質よりも収量を多くというのが現状です。野菜もお米も、食べる人との関係を増やすことが環境へも優しい農業となるのです。
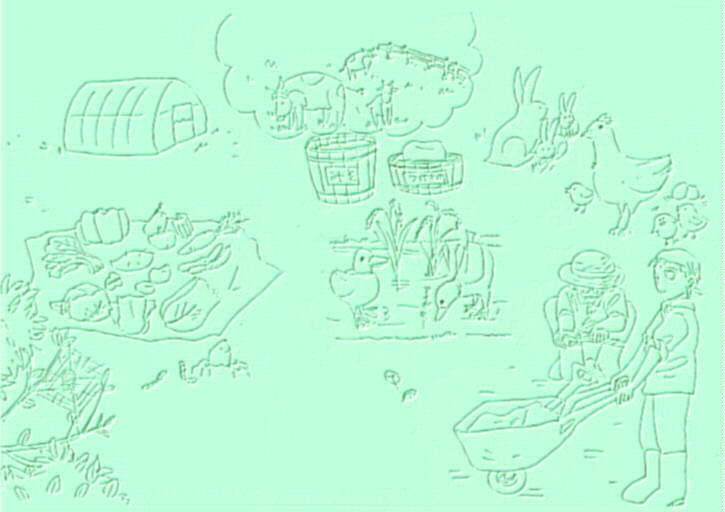


コメント