かけだし情報1200
- Hiroaki Ehara
- 2019年10月24日
- 読了時間: 4分
畑情報
台風がシーズンになり、日本は毎週のように台風がやってきます。千葉県を直撃した台風の被害は想像を超え、いまだに停電や断水など、生活に欠かせないインフラを直撃しました。関東に直接やってくる台風はめったになく、勢力が強いまま直撃するとどうなるかを改めて認識させられました。
台風、大雨、干ばつなど極端な天気が増加している背景には温暖化があると言われています。人間の生活を豊かにするための経済活動は、一方で各地の環境を破壊してしまいます。
アマゾンの熱帯雨林は、家畜の餌用の穀物栽培、ハンバーグや肉用の牛の飼育などを目的に気が燃やされ、ものすごい勢いで木々が減少しています。地球の酸素の20%を供給しているともいわれるアマゾンの森がなくなることは、近い将来の生き物の暮らしが大きく変わることにもつながります。頻発する自然災害によって失われる多くのものを守るには、自分たちの暮らしをしっかりと考えることが必要です。
このところ、お天気が安定せず、数日おきに雨が降ります。田んぼでは稲刈りが始まり、週末になると多くのコンバインが稲刈りをしています。
うちの田んぼも早生の品種であるキヌヒカリの稲刈りをしました。ちょうど気温が30度を超える暑い日で、田んぼの四隅を刈るだけでも汗が吹き出すくらいの陽気でした。稲を刈るタイミングはいくつかのポイントがあります。品質や味を重視するのであれば、少し早めに刈るのが良いと言われます。ただ、早く刈ると籾が十分に熟していないものが多くなり、収量はやや少なめになるのがマイナスです。
一方、刈り取りを遅くすると熟した籾が増えるので
収量は増えると言われます。でも、あまり刈り取りす遅らせると籾が乾きすぎてしまい、玄米の状態になったときに割れてしまうものがでてくるのです。農家にしてみればできるだけ収量を増やし、収入も上げたいという思いがあるので、ぎりぎりまで稲刈りを遅らせる人もいますが、本当は適期に刈り取るのが一番です。
この適期を見極めるのは難しい部分があります。まず、田んぼの何か所かで稲の穂の状態を見ます。稲穂は先の部分から熟していき黄金色になります。穂全体が黄金色になるまで待つよりは、穂の元の部分が10
%ほど青いときに刈るのが適期をされています。
また、稲の水分量を測る機械を使い、水分が25%を切った時が刈り取り時期と言われます。つまり、目で穂の状態を確認し、水分量を測ることで適期を判断することになるのです。
もう一つ、稲刈りの時期を判断する方法があります。それは稲が出穂してから積算温度で1000度になった時が刈り取り適期というものです。積算温度は、日々の平均気温から一定の基準値を超えたものを合計した温度です。計算方法もありますが、難しいので、農家によっては積算温度計なるものを使って判断しています。今は、ウエブサイトで地域ごとの積算温度を計算してくれるサイトもあるので、出穂時期を確認しておけば、簡単に計算してくれます。
今年は出穂期をきちんと確認していなかったので、このサイトの積算温度計算はできなかったのですが、見た目と水分計で判断し、稲刈りをすることにしました。コンバインで刈り取り、いっぱいになった籾は軽トラックに積んだ籾運搬用のコンテナに移します。
コンテナから乾燥機に移して感想を始めます。この時点で乾燥機は水分量を計測し、どのくらいの乾燥時間になるかを表示していくれます。
乾燥機の水分計では籾の水分は約28%、家にある水分計よりも多めの表示でした。収穫目安である25%よりは多い水分量でしたが,乾燥機で14.5%まで乾燥させました。28%も水分があると、保存中にカビがはえてしまい、長期の保存はできません。機械乾燥でなく、天日で乾燥させるほうが水分が少しずつ抜け、葉や茎にある栄養も籾へと移るのでおいしさが増すといわれます。機械による急激な乾燥が一般的ですが、多くの田んぼを管理するなかで天日干しをするのは、かなりの手間が必要になるからです。
乾燥が終わり、籾摺りをした玄米はきらきらときれいです。収量は少なめでしたが、今年最初の収穫ができたことに感謝です。
10月13日の稲刈りは天日に干します。太陽の光をいっぱいにあべて乾燥されるお米は格別だと思います。稲を刈りながら、太陽の恩恵を感じる時間になると思います。
稲刈りのご案内
今年の稲刈りは10月13日、日曜日です。午前9時頃から始めています。参加費は昼食込みで大人一人 1500円です。皆さんの参加をお待ちしています。
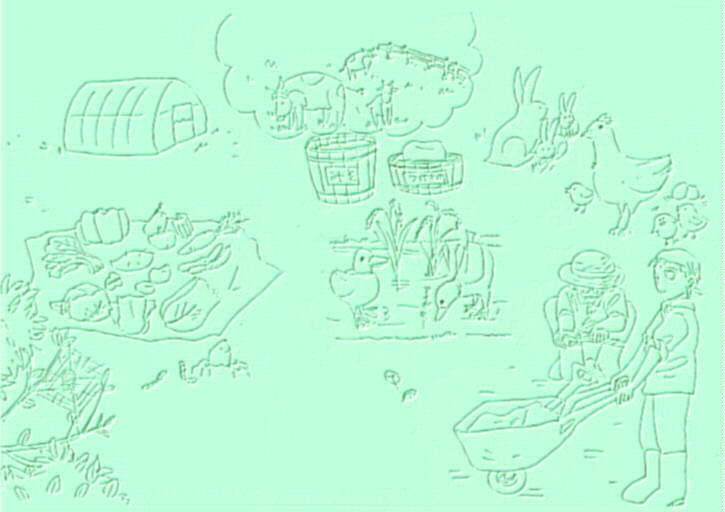


コメント