かけだし情報1197
- Hiroaki Ehara
- 2019年10月24日
- 読了時間: 4分
9月
畑情報
暦は9月となりましたが、まだ残暑は厳しい日が続きそうです。秋雨前線や台風など、9月は大雨が心配される時期でもあります。稲刈りや秋冬野菜の種まき、植え付けなど農作業が集中する時期だけに、お天気次第で作業に大きく影響が出るのも9月です。
まだ夏は終わっていませんが、今年は本当に雑草の伸びるのが早く、草を刈っても刈ってもすぐに元に戻ってしまいます。伸びた草を刈り、トラクターで耕しておけば雑草も土の中で堆肥となっていきますが、きれいに分解するまではある程度の時間が必要です。雑草の種類によっても分解の速度は違います。本当は草が種をつける前に刈り、それを土に戻すことができれば良いのですが、どうしても後手に回ってしまい、気がつくと大株になっている雑草もあるくらいです。
雑草対策の有効な方法として太陽熱を利用した太陽熱消毒というものがあります。特に秋播きの人参にこの方法を利用する有機農家も多くいます。
太陽熱消毒とは、文字通り太陽の熱を利用して雑草が発芽できないようにすることです。梅雨の雨を利用することが多いのですが、あらかじめ堆肥など肥料を散布し、トラクターで耕して畝も作っておきます。そして雨などで十分に土を湿らせておいてから透明なビニールマルチを張ります。梅雨明け後の強烈な太陽がビニールを通して照り付けるため、土の中は高温となり、雑草の種や虫の卵などが死んでしまいます。そして、人参の種まき時期になったらビニールを取り、そのまま種まきをします。しばらくすると人参は発芽しますが、雑草の種は死滅しているので、その後の除草をする手間がいらないのです。
ただ、この方法では、土の中にいる微生物も死んでしまいますから、一時的には土のなかは無の世界になってしまい、そのことを嫌う有機農家もいます。広い面積に人参を作ると、この除草作業だけでも大変です。前に訪問した農家は、シルバー人材の人を数人頼んで、1週間ほど草取りをしてもらい、その費用もばかにならなかったと話していました。
有機農業の技術はそれぞれの農家の経営方針や地域の状況、その人が目指す有機農業によって異なります。ある程度の基本的な技術は確立されてはいますが、それは個々の有機農家の経験によって成り立っているものです。
日本で有機農業のことを学べる場所は、学校としては本当に限られたものです。それは有機農業の特徴でもあるのですが、地域による違いや、どんな有機農業をするかによっても違うため、一般的な農法のようにマニュアルがないのです。米や野菜でも、いつ、どのくらいの肥料を散布し、この時期に追肥をし、農薬はいつ、何を使うというのがマニュアルとして存在します。JAなどは、JAが作ったマニュアル通りに肥料を使い、農薬を使わないと収穫したものを引き取らないというところも多いのが現状です。
有機農業を教えることのできる先生も限られています。そのため、多くの新規就農希望者は有機農家の研修生として学ぶのがほとんどです。埼玉県では、県立の農業大学校に有機農業コースが開設されています。1年間のコースですが、毎年、15名前後の学生さんが在籍しています。この夏も、一人の学生さんが1週間ほどガバレで研修を受けていきました。他には、島根県の農業大学校、私立では茨城にある日本農業実践学園、高校では三重県にある愛農学園くらいでしょうか。うちの次男が勉強していた茨城の鯉渕学園は、残念ですが、有機農業コースをやめてしまいました。
有機農業を始めたいと思い、研修や勉強をしている人たちが次にすることは農地を探すことです。その人の求める有機農業を実践するにふさわしい場所を探すことができれば良いのですが、そうすんなりとはいかないようです。中山間地の自治体などが農業を志す人を受け入れることもありますが、多くの場合が、有機農業に対しては懐疑的です。その地域の特産品である野菜などを作る人を受け入れるのであった、有機農業はだめですとなる場合が多いのです。
ガバレのある地域でも、遊休地となっている農地が点在しているところがあります。農地を大きくできる所は大規模農家が耕していますが、大きな機械が入れないようなところは大規模農家も借りません。そういう場所は有機農業に向いているともいえるのですが、誰かの紹介でもないと、見ず知らずの人に農地を貸すのは消極的な農家が多いのも現状です。今後、5年もすれば、今、主力で農作業をしている70代が農業をやめるケースが増えてくると思われます。中山間地でなく、ガバレの周辺でも農地をどうしていくかを検討する必要がでてくるのは必至です。
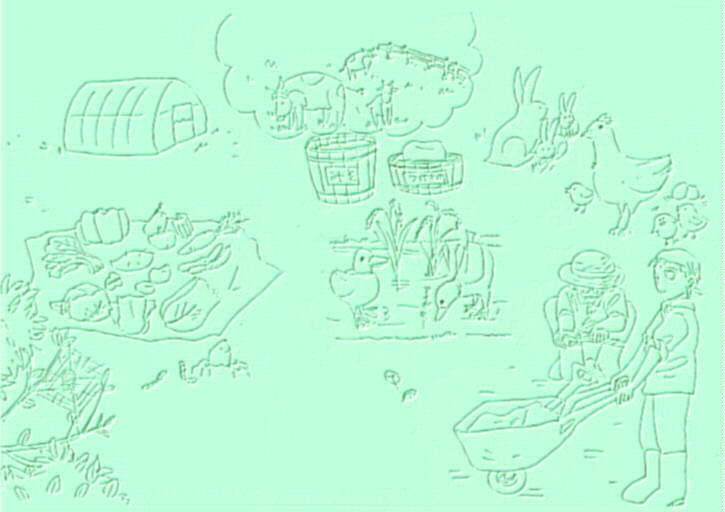


コメント