かけだし情報 1310
- gabarehiroba2
- 2022年4月10日
- 読了時間: 4分
畑情報
先週は木曜日に雪が降り、日曜日の夜からも雪が降る予報になっています。木曜日の雪は大雪との予報も出る中、途中から雨になって積もることはありませんでした。今夜からの雪がどのくらいの積雪になるのか心配ですが、ハウスの雪下ろしをしなくてすんでほしいと願うばかりです。
そして、今週末にもまた湾岸低気圧がやってくる予報がでています。2月も後半になると暖かい日もあるのですが、今年はまだ寒さが続くとの予報ですから、もうしばらくは低気圧がやってくるたびに雪の心配をすることになるかもしれません。
それでも、太陽の光は春の気配を感じさせるようになってきています。真冬の凛とした光から、少しほんわりとした空気感に変わってきています。まだ三寒四温という状況ではありませんが、少しずつ季節が移っていくことを感じることができそうです。
去年より体感的には寒さが厳しいのですが、今年も夏野菜の種まきを始めました。去年の作業日誌を確認すると、ハウスの中で大根の種まきをしたのは1月末でした。そして夏野菜の種まきを始めたのは2月14日となっていました。
今年は寒い日が続いているので、ハウスでの大根の種まきは少し遅らせて、2月に入ってからとし、13日に大根とカブを播きました。電熱マットで育苗をしていた小松菜と水菜の苗もハウス内に植え付けました。そして、トレイにピーマン類とレタスの種をまき、約30度に設定した電熱マットにトレイを置きました。今週中にはナスの種もまき始める予定です。
ピーマンやナスを畑に植えるのは5月の連休ごろですから、これから約3か月間の育苗です。電熱マットにはもう少し空きスペースがあるので、キャベツや小松菜などの葉物野菜を育苗していく予定です。
電熱マットはスペースが限られているので、主に発芽から本葉が出るまでの育苗に使います。その後は育苗ハウス内に落ち葉を主体とした踏み込み温床を作り、苗が大きくなるまで育てます。全部で4回ほど踏み込み温床を作っていきますが、最初の温床は来週初めくらいに準備することになりそうです。
さて、自然と共生すべき農業ですが、逆に自然や生態系を大きく壊していることも多くあります。それは農業の効率化や高齢化とも大きくかかわっている課題でもあります。その一つの例が稲作で使われている肥料の問題です。
JA全農が「2030年にはプラスチックを使った被覆肥料に頼らない農業」を掲げたとの記事を読みました。プラスチック被覆肥料というのは、お米を育てるときに使う肥料の一つで、田植えの時などに使えば、その効果が稲の生育に合わせて持続するというものです。
お米を育てる場合には、田植えをする前などに最初の肥料を田んぼに散布します。その後、稲が成長し茎内部に穂の赤ちゃんである幼穂ができる時期に、追加の肥料を散布します。この時期に肥料を上げることで穂の大きさや籾の数が決まるので、とても大切な肥料と言われます。ただ、この肥料を散布するタイミングは7月の梅雨明け前後になることが多く、猛暑のなかでの肥料散布は体力的にもとてもきつい作業です。
そこで登場したのが肥料をプラスチックで覆った一発肥料といわれるものです。肥料一粒一粒が二重構造になっていて、田植え前後に溶け出すものと、ちょうど幼穂が作られるころに成分が溶け出すようにプラスチックでコーティングされているものです。
一発肥料を使うことで夏場の重労働から解放されるために、この肥料は全国に普及しています。
ところが、肥料が溶け出した後の被膜殻であるプラスチックが水田から流れ出し、排水路から川へ、そして海へと流れ出していることが海洋汚染につながっていることがわかってきました。ある調査によると20年度のマイクロプラスチックの流出は、日本国内から年間で157トンと言われています。内訳で多いのは質量比で、人工芝の23%に次ぐ、15%を占めている結果がでています。
この海洋汚染を防ぐためには代掻き直後に被膜殻を田んぼから出さないような対応を農家がする必要があります。プラスチックをすくいとる、排水口にネットを設置するなどの対策です。また、プラスチックを使わない肥料も開発されているようです。
ただ、農家はこの一発肥料が海洋汚染につながっているという認識を持っていないのが現状です。肥料メーカーも農家に対しては、肥料が海を汚しているとは伝えません。
うちも宅配では新聞紙を使いますが、お店に置かせてもらうときはまだプラスチック袋です。紙やプラを使わないような対応を検討しないといけないと感じています。
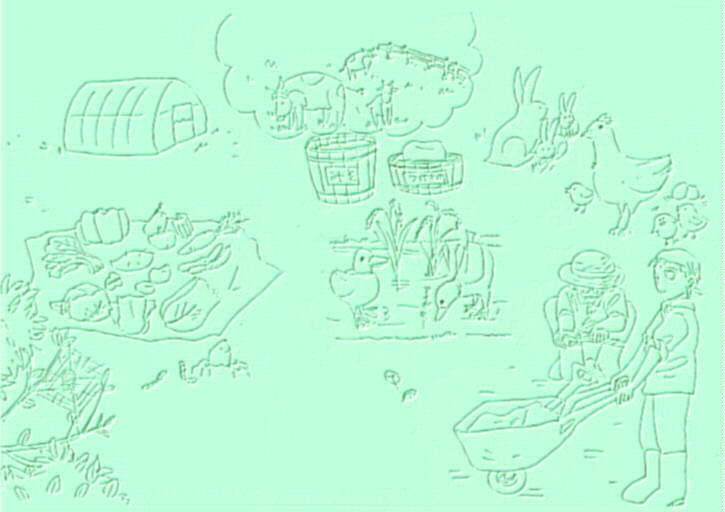


コメント