かけだし情報 1307
- gabarehiroba2
- 2022年4月10日
- 読了時間: 4分
畑情報
大寒も過ぎましたが、寒さの厳しい日は続いています。北風の強い日などは体感温度はさらに低くなり、足元から冷たさが体の中まで伝わってきます。
そんな時は、育苗ハウスなどに避難して、しばし暖かさを感じるようにしています。
大寒といえば、ついこの前知ったのですが、その日に産んだ卵を食べると縁起が良いのだそうです。
御利益は健康と金運です。大寒のころは一年でも寒さが一番厳しい時期です。鶏は餌の食いつきは良くなるのですが、寒さから身を守るために産卵は極端に少なくなります。いっぱい食べた餌の栄養が、少ない産卵の卵に詰まっているので、とても貴重なものになっているようです。うちの鶏たちも、前日までは少ないながらもそこそこの数の産卵がありました。ところが、大寒の日はわずか12個と、急に数が減ってしまいました。それ以降も10~20個くらいの低調な産卵となっています。
ただ、この大寒の卵も平飼いや、外気に接するような作りをしているケージ飼いの鶏に言えることで、現在の大規模な養鶏場のように、窓もないような建物のなかで、温度も一定に保たれているような鶏には無縁の話です。季節を感じながら一生を送れる鶏たちは全体の数%ほどかもしれません。
写真は発芽したばかりの小松菜です。先週のかけだし情報で載せた電熱マットを使った温床で発芽したものです。小さなビニールハウスのなかに木枠を作り、そこに籾がらを15センチほど敷き詰め、さらに発泡スチロールの板を乗せたところに電熱マットを置いています。夜には寒さを防ぐためにビニールで覆って保温しています。種を播いて3日後には小さな芽が見えだし、それから数日するとしっかりと双葉を広げてくれます。
農業は自然と共存しているといわれますが、同時に自然を一番破壊している現場でもあります。耕作できずに放置された畑や田んぼなどはすぐに草で覆われていきます。その草の植生も徐々に変化して、大型の草たちが主役となっていきます。さらに、草から雑木へ、そしていつかは森林へと変わっていくのが自然の状態です。
その自然にさからって、人間が必要とするものを育てているのが農業です。さらに言えば、せっかく育てた命をすぐに奪っているのも農業です。野菜は人が食べやすいように改良を重ねられたものですが、そのままにしておけば花を咲かせ、種をつけ、次世代へとその命を引き継いでいきます。野菜が花を咲かせる前に畑から収穫し、その野菜の命を頂くことで自分たちの命をつなぐのが農業です。
そんな命を頂く農業にたずさわる者として、せめて作物が気持ちよく育つよう、土を豊かにし、作物を愛しむのせめてもの償いのような感じがします。
まだ寒さの厳しい中で、人工的なものを使って発芽をさせるのは、野菜にとっては望ましいことではないのかもしれません。いつも人間の側に立ってしか農業を見ていないのですが、種まきが始まるこの時期だけは、野菜の気持ちを考えてしまいます。
さて、先日の日本農業新聞の論説に、直売場出荷者の確保、という記事が載っていました。新鮮で身近なところで生産されたものが買える直売所や道の駅は人気の場所ですが、出荷者が高齢化し運営が厳しくなっている、という内容です。
ある団体が、全国の直売所を対象に実施した調査では、運営上の課題として一番多かったのは「出荷者の高齢化」で9割近くを占めているそうです。高齢化により、出荷を縮小したり、やめてしまったりというケースが増えているのです。
それに対する取り組みをしているところも紹介されています。中山間地の農家が直売所のあるところまで出荷品を運ぶのが困難なケースもあり、それを解消するためにJAが出荷品を運ぶ取り組みをしているところもあります。また、新たに出荷してくれる人を増やす試みとして、地域の住民に農業を学んでもらう農業教室を開き、新規就農者を育成するところもでてきています。
鴻巣市でも4年後に道の駅が開業する予定です。市内は米や麦、花は盛んですが、野菜の取り組みが少ないのが現状です。道の駅への出荷も見据えながら、有機農業による取り組みで何ができるか、どうしたら人を増やせるか、考えていきたいと思います。

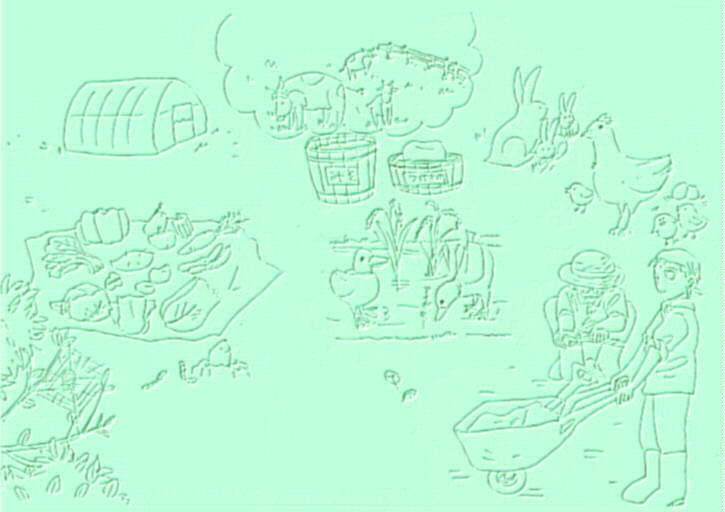


コメント