かけだし情報 1301
- gabarehiroba2
- 2022年4月10日
- 読了時間: 4分
畑情報
今年も残りひと月となりました。本当に時間の経過が早く感じます。12月は農作業もひと段落し、今年のお米や野菜についての見直しと、翌年にむけての計画を考える時期です。とはいっても、農業はお天気によっても大きく左右されることもあり、同じように種を播いても、出来が全然違うなんてこともよくあります。それでも、新しく取り入れたものがうまくいったり、逆に全然だめだったこともあるので、次に向けての改善点を見つけていきたいと思います。
お米については、今年は買い取り価格が大幅に下がり、このままでは来年に向けての米つくりの意欲を削ぐような状況でした。例年、収穫したお米は合鴨米以外は近所のお米屋さんに出荷していました。でも、今年はお米屋さんも、売れる人は自分で売ってほしいということで、買取については消極的でした。そのため、今年は全量を自分たちで売ることにしました。今年は、栽培方法を変えたところも多いので、味や収量がどうなるか心配でした。
これまで慣行栽培で作っていた田んぼも、埼玉県の特別栽培の基準を満たし、加えて、できるだけ有機に近づけるために肥料も特別栽培に準じたものにしました。特別栽培の基準では、お米を栽培するときに大切な窒素成分のうち、化学肥料の割合を50%以下にする必要があります。また使える農薬の成分も慣行栽培では12回(成分)なので、その半分6回までは可能ですが、うちでは除草剤1回分、2成分としています。
野菜でもそうですが、肥料などを変えたからと言って、急にすべてが変わるわけではありません。作物を育てるのは土なので、その土が変わるまでに少なくとも3~5年、あるいは10年かかる場合もあるといわれます。今回の特別栽培用の肥料でも、3年くらいは継続して使うことで、やっと効果が出てくるという話を肥料屋さんもしていました。
話をお米の味に戻します。獲れたての新米ということもありますが、試食したお米はどれも「おいしい」と感じました。家族以外で食べた方からも、甘くておいしいお米だった、と好評でした。そんな時に、肥料屋さんからお米の食味検査をしてみないかと言われました。
お米のおいしさは、見た目、炊き方、水加減なども含め、その人の主観的なものも大きく影響しますが、お米自体に含まれる成分によっても違います。
そこで、食味値を検査する分析機を使って、アミロース、タンパク質、水分、脂肪酸度を測定し、総合的な点数をつけるのが食味値検査です。
この味値は100点満点で表し、数値が高いほどおいしいお米と言われます。最近は食味の良いお米が次々と開発されていることもあり、また、農家の努力もあって、日本産では、65~75点が標準になっています。70~80%の人が美味しいと認めるのは70点以上のお米と言われています。
お米の主成分であるデンプンは、2割のアミロース(硬さの成分)と8割のアミロペクチン(粘りと柔らかさ)からできています。もち米は100%アミロペクチンで、粘りがあるお米です。粘りのあるお米が美味しいと感じる人は、アミロースの割合が低いお米が良いことになります。コシヒカリはこの数値が16~17くらいです。
タンパク質は水を通さないので、お米の吸水を阻害します。タンパク質が少ないお米は吸水が良いため、炊き上がりがふっくらとします。玄米のタンパク質の平均は6.8%と言われます。栽培の時に窒素をたくさん使うと収量は多くなりますが、値も大きくなるためにお米がまずくなる原因となります。
水分は16%が基準で、水分が高いほどおいしいいお米となります。ただ、長期保管をするために、出荷の際には水分量を15%以内にする必要がでてきます。そして、脂肪酸度は時間が経つにつれて数値が高くなります。新米では10~20㎎が標準です。
今回、検査してもらったガバレのお米は、合鴨米が82、他のお米は73~81でした。アミロースの値はどのお米も適正値で、タンパク質は一つの品種以外は適正値でした。値が73の田んぼは、去年田んぼに病気がでたところで、少し窒素成分が多く残ってしまったようです。数値が低かったのが水分量で、この値がもう少し高ければ全体的に値が高かった気がします。あまり数値にとらわれることはしませんが、数値を上げることが適切な施肥や管理につながるので、この食味値を参考にしながら次の米つくりを考えたいと思います。
最後にお願いがあります。今年は自分たちでお米を売らないといけません。少しでも良いので、是非、購入にご協力ください。また、お知り合いにもお声がけをお願いします。よろしくお願いします。
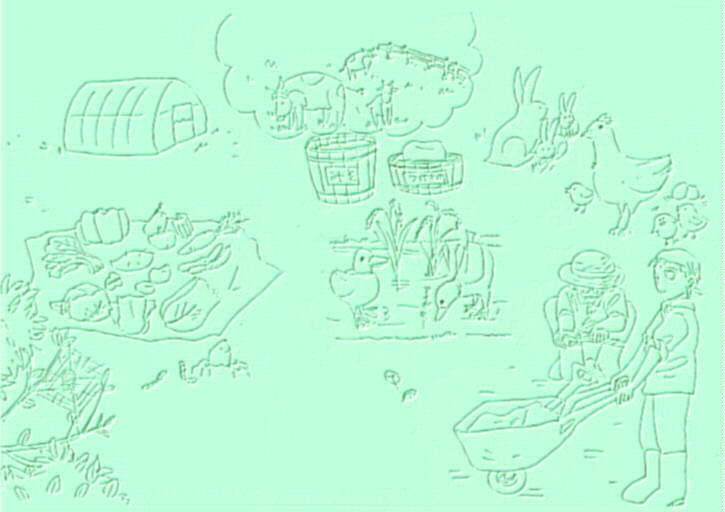


コメント