かけだし情報 1282
- gabarehiroba2
- 2022年4月10日
- 読了時間: 4分
畑情報
今週は梅雨入りの発表があるのでしょうか?例年より早い梅雨入り宣言が出された地域もありますが、関東は梅雨を思わせる雨の日が続いた後は真夏のような暑い日となり、しばらく雨らしい雨が降っていません。今年もお天気に一喜一憂する日が多くなりそうです。
先週は週末から田んぼの準備でバタバタとしていました。稲の苗を植えるための代掻きはそれぞれの田んぼで2回ずつ行いました。最初の代かきは荒代と呼ばれ、それまでの乾いていた田んぼに水を入れ、田んぼの土をこねていく作業です。続いて植え代と呼ばれる2回目の代掻きをしました。これは田植えがスムーズにできるように仕上げの代掻きです。
代掻きの終わった田んぼに苗代から稲の苗を運ぶ作業は土曜日の午後と日曜日の午前中に行いました。土曜日は午前中に有機農業教室があったため、午後になってからの苗運びとなりました。
軽トラックの荷台に苗を運ぶための棚を乗せ、そこに苗代で育てていた稲苗の箱を積み込んで田んぼへ運びます。今年田んぼへ植える苗は全部で6種類。見た目ではどの苗も同じように見えるため、それぞれの種類ごとに苗を運び出します。もし違う種類の苗がまじってしまったら大変です。それは、種類によって早生、中生、晩生と生育期間が異なるからです。もし、早生の種類と晩生の種類が同じ田んぼに交じってしまったら、稲刈りをしようと思っても、刈り取り時期が違うため、一つの種類は稲刈り時期でも、別の種類はまだ熟していない状態になるからです。
ただ、農家によっては早生の違う種類の稲を同じ田んぼで育て、最初からブレンドしたお米を収穫するということを実践している人もいるようです。
この稲運びは結構大変な作業です。水の張っている苗代から稲の苗箱を運ぶのは足を取られ、さらに水分を多く含んでいる苗箱の重さもあるからです。軽トラックに積んだ苗箱を種類ごとに割り当ての田んぼへ運び、田植えまでは田んぼの水の中で入れておきます。
外に置いておくと苗箱の土が乾いてしまい、それが長く続くと稲も刈れてしまいます。田植えの直前に田んぼから畔に箱を上げ、田植えに備えます。
そして月曜日、田植えを始めました。稲の苗は本葉が3枚、そして4枚目が半分ほどに育った状態の中苗と呼ばれる大きさです。種まきをしてから約30日の苗です。田植えは田植え機を使って行いました。
うちの田植え機は5条植え、一度に5条の苗を植えていく乗用タイプです。田んぼの大きさなどにもよりますが、2条植えで歩行タイプの田植え機から、大きいものでは一度に8条を植えるタイプ、そしてさらには、
GPSを搭載した自動運転田植え期まであり、大規模に稲作をしている農家は8条植えを使っています。
今年の田植えには次男も手伝いに来てくれ、田んぼ全体の6~7割は次男が田植え機に乗ってくれました。
初めての田植え機操作でしたが、結構きれいに、まっすぐに植えていました。特に有機の田んぼでは、これから除草機をかけるので、まっすぐに植えていないと作業がしずらいため、田植えをきれいにするのは必須です。
田植えは5条植えていったら反転して次の5条を植えるという作業を繰り返します。まっすぐに植える目印として、田植えをしながら次のラインを示すマーカーというもので田んぼにラインをつけていきます。水が少ない状態であれば、マーカーでつけたラインが良く見え、それにそって田植え機を操作すればよいのですが、水が多いところではラインが見えなくなり、まっすぐにするのが大変なこともあります。特に風のある日は水面が波立ち、集中して水面を見ていると船酔いのような感じになることもあり、集中力を持続させるのは大変です。
今週は有機の田んぼに除草機を入れる予定です。田植えからおおよそ1週間で1回目、それ以降は週に1度のペースでひと月ほど除草します。中古の田植え機に取り付ける除草機を使ってみるのですが、果たしてどのような効果があるのか。そして家の前の田んぼでは合鴨も放鳥する予定です。まだしばらくは田んぼの作業が続きます。

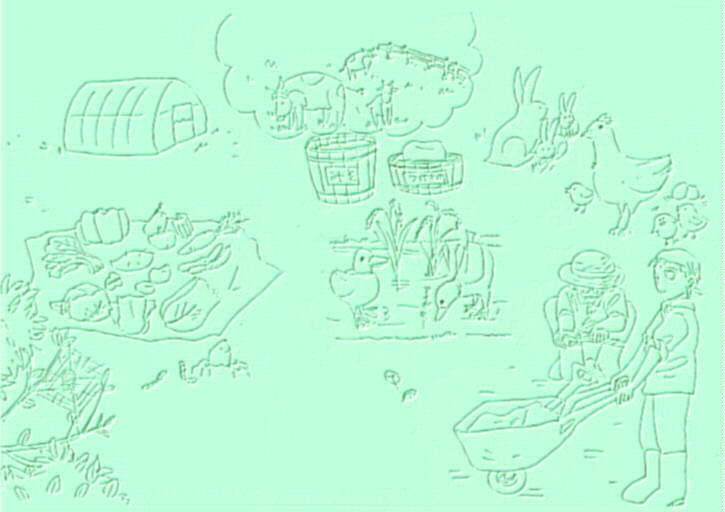


コメント