かけだし情報 1278
- gabarehiroba2
- 2022年4月10日
- 読了時間: 3分
畑情報
週末は一気に夏が来たような暑い日になりました。土曜日は有機農業教室が午前中にあり、午後は稲の種もみを播く育苗箱に土を詰める作業をしました。そして日曜日は種まき作業と、お手伝いに来てくれた人たちも暑い中での作業となって疲れたことと思います。
米つくりの中でも種まきは重要な作業のひとつです。苗のでき次第でその後の生育にも影響がでてしまうからです。昔から「苗半作」と言われ、作物の生育の中で苗つくりが大切とされてきました。野菜であれば種まき後の生育が良くない場合、再度種まきをしても間に合うことが多いのですが、稲の場合は購入した種籾も作付けに合わせた量しかありません。そのため、苗つくりの失敗すると取り返しがつかなくなります。
出来のよくない苗が少しの場合は、いつも多めに苗を育てているのでどうにかなりますが、全体の2割以上となると困ってしまいます。種を播き、芽が出そろうまでは心配な時間が続きます。
さて、稲の種籾は種まきまでに何度か作業をしないといけません。最近、うちではしていないのですが、自家採種した種籾の場合は、塩水選といって、塩水に種を入れ、浮きいる苗を取り除く作業を行います。中身のない種籾は播いても芽は出ませんから、しっかりとした種を選ぶための手段です。塩の濃度は卵を浮かべてみて判断する方法があります。
次に種籾の消毒です。今では温湯消毒といって60度のお湯に10分間籾を入れる方法が増えてきました。農薬を使う回数を減らすためです。種籾には病原菌が付いている場合もあり、そのままでは苗の病気がでることがあります。それを防ぐために温湯消毒や、農薬による消毒をすることになります。
温湯消毒が終わったら、次は種まきに合わせて種籾を水に浸ける作業を行います。水に浸けるのは水の積算温度が100度になるまでです。例えば、ある日の水の温度が15度とすると約7日間で100度を超えます。春先にこの作業をする東北地方などでは、水の温度が10度以下になることもあるので、その分長い時間水につけないといけません。ただ、10度以下になると種もみが発芽するによくない影響もあると言われ、水温を15度などに設定できる催芽機という機械を使っている農家もあります。
水から上げるタイミングは、種籾の種類によって違ってきますが、稲の胚芽部分がちょうどハトの胸のように膨らみ、白い芽が見え始めるころです。寒い時期に水に浸ける地域では、100度の積算温度になり、ハトムネのような状態が見えたら30度くらいのお湯につけて芽がでるのを進める「催芽」作業をしています。うちの場合、5月にはいってからの浸種なので、水温も17~18度になり、最後に30度につけなくても芽が出てくる状況です。
昨年の育苗では2種類の稲の発芽率が悪く、田んぼへの植え付け計画を見直すことになりました。原因として考えられるのは、水に浸けている時間が少し足りなかったことです。品種によって100時間では足りないものもあり、種もみを入れた袋ごとに状態を確認することが必要でした。
その反省から今年は水温を測る回数を多くし、100度に近づいてきたら籾の状態をしっかり確認することにしました。5月1日に種もみを水に浸けてから6日目、籾の中に白い芽が出ているものがちらほらと確認することができました。そのまま夕方まで待って水から上げました。他の品種はもう少し待ったほうが良さそうだったので、翌日とさらにその翌日に浸種を止めました。
種まきは9日に予定していたため、種もみは洗濯機で脱水してから冷蔵用の部屋に保管しました。そして苗箱に土を入れる作業を土曜日の午後に行い,日曜日は種まきをしました。育苗箱に種を播き、それを苗代に並べてから不織布、さらにシルバーシートをかけて種まき作業は終わりです。
今年の発芽がどうなるか、まだ心配は続きます。次回には種まきやその後の様子をお伝えします。

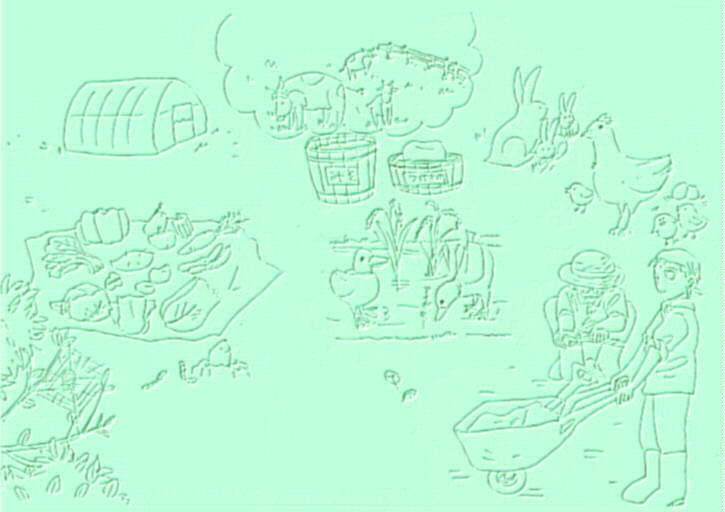


コメント