かけだし情報 1269
- gabarehiroba2
- 2022年4月10日
- 読了時間: 4分
畑情報
2021年もコロナ禍との付き合いで始まり、気がつくと1年の6分の1が過ぎてしまいました。まだ寒さの厳しい1月、2月は農作業のそれほど忙しい月ではありませんでした。でも3月の声を聞くといよいよ忙しい季節の始まりを感じます。
今年は電気マットによる育苗をしているので、例年よりも早めの種まきをした野菜が多く、育苗ハウスの中ではキャベツや小松菜、レタスなどの葉物野菜が植え付けを待っています。今週中には植え付けをする場所に堆肥を撒き、畝を準備していきます。その後、雨の予報を見ながら畑に苗を植え付け、キャベツなどは防虫ネットをかけていきます。この時期、まだ虫たちは活発ではありませんが、お腹をすかしているのは虫だけでなく、鳥たちもついばむものを探しています。いったん見つかるとあっという間に食べられてしまうこともあるからです。
3月になると畑に直接種を播くこともできるようになります。気温も少しずつ高くなり、雨も適度に降ってくれるようになります。そうすると野菜と一緒に草たちの種も目を覚まします。冬の間、茶色一色だった畑も緑色が増えてきて、生き物のエネルギーを感じるようになってきます。
先週の月曜日、飯能にある野口種苗さんに種を買いに行きました。この野口種苗さんは有機農家や固定種に興味のある人にとっては有名な種屋さんです。野口さんは種についての本も出されており、種の自家採種を含めて全国で講演をされています。お店は飯能の市街から山の中に入った入間川の川岸にあります。全国から種の注文が入り、それを発送したりお店を切り盛りしているのは若い人たちです。
4月から開始する有機農業教室ではできるだけ固定種の種を使っていくことを考えています。ガバレ農場自体は固定種も使いますが、F1と呼ばれる交配種も使っています。固定種を使い、可能な限り自家採種も教室のなかで試してみたいと思っています。
写真の左側は野口種苗で購入した固定種で、相模半白というキュウリです。右は大手の種苗会社であるサカタのタネが販売しているキュウリの種で「うどんこ病に強いきゅうり」という名前です。きゅうりというと緑色で長さも太さも同じものばかりですが、固定種のキュウリは大きさも太さも色も様々です。個性的な物が固定種には多い気がします。
種の自家採種は毎年試みてはいますが、できているのは全体のほんの一部です。大豆などの豆類は比較的種とりのしやすい分類です。トマトやナスも数品種ですが、種とりをしています。ただ、種とりをしたものを作り続けるにはちょっとしたエネルギーが必要だと感じています。この種は毎年取り続けるというようにして、そこに労力をかける余裕がないと思うようにいかないのが常です。
また、アブラナ科のように交配しやすいものは種をとっても、それが本来の固定種の形質を受け継いでいるかがわかりません。虫や風によって近くにある別の品種の花粉が受粉していることもあるので、ついつい種を買う方を選んでしまいます。
有機JASでは種も有機圃場由来のものであることが規定されていますが、現実の問題として有機の種をすべての品種で購入することは難しいため、有機以外の種の使用も認められています。ただし、有機の種を使えない理由が必要にはなりますが。
ここ数年、天候の異常が著しくなっています。その土地で受け継がれてきた固定種の種も、この天候不順に対応するのが難しくなることも考えられます。それでも温暖化する中で良く育つ個体も出てくるでしょうから、その種を取り続けることで温暖化に対応できるようになる種もあるかもしれません。
種を取るには実が熟すのを待つ必要があります。トマトやナスはあまり形は変わりませんが、写真のキュウリはちょっと違います。種を取るにはキュウリが巨大化するまで置いておきます。太さも直径が10センチほど、長さも50センチほどにまで大きくなり、色も黄色に変化します。いつも食べているキュウリからは想像できませんが、種がしっかりと熟すにはその大きさが必要になってくるのです。もともとキュウリはその大きさで食べるのが美味しいのかもしれません。


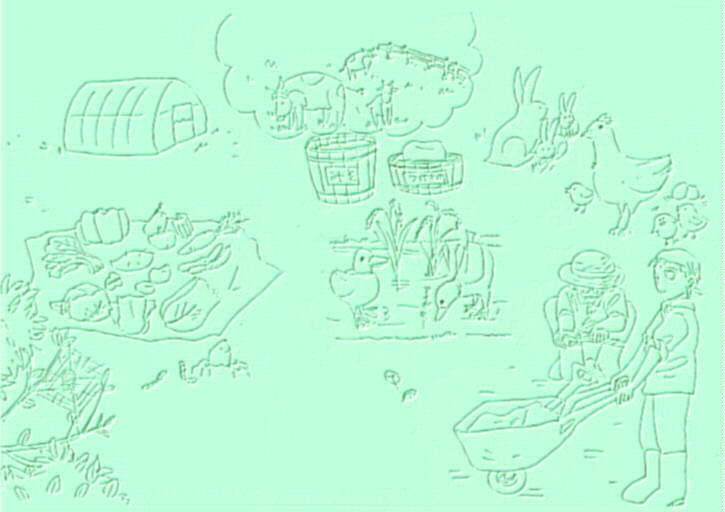


コメント